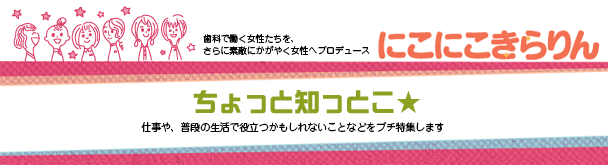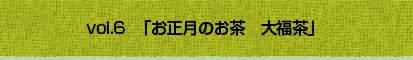
お正月は実家でゆっくりお正月を過ごすスタッフさんも多いのでは。
こたつに入ってお茶とみかん、なんてくつろげたらいいですね。
ところで、お茶にはお正月に古くから飲まれている「大福茶(おおぶくちゃ)」というものがあるのをご存知ですか?
今回は、この大福茶についてご紹介します。
大福茶が飲まれるようになったのは、平安時代。都に疫病が流行したとき、ある僧が病者にお茶を与えたところ、疫病が治まったそうです。
これにあやかり、時の村上天皇は正月元旦にこのお茶を服されるようになり、「王服茶」と呼ばれました。
そしてこのお茶は、幸福をもたらし新年を祝うお茶「大福茶」としていつしか庶民にも広まり、今日まで縁起の良いお茶として伝えられています。

大福茶というのは、実はお茶の種類ではありません。
そのため、お茶屋さんによって詰められるお茶は、煎茶、玄米茶、ほうじ茶、などさまざま。飲み方は結びこんぶと梅を入れるのが一般的なようです。
また、茶道が盛んな京都では、井戸でくんだ若水を使うこだわり派の人もいるとか。
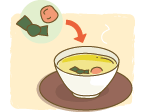
お茶の入れ方は種類によって若干異なりますが、ここでは日本茶生産量8割の最もポピュラーなお茶、煎茶の入れ方をご紹介します。 ひと手間加えた入れ方をすれば、さらにおいしく味わえますよ。
 |
煎茶は約70度が適温です。沸騰した湯をやかんから茶碗八分目ほど注ぎ、温度を下げるのが基本です。 |
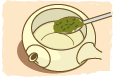 |
煎茶ひとり分は、ティースプーン1杯(約2g)が目安です。 |
 |
移しかえることで、ちょうど適温の約70度くらいになります。 |
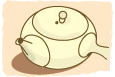 |
急須を揺らさずに、そのまま待ちましょう。 |
 |
濃さや味が均一になるよう、茶碗に少量ずつ注ぎます。二煎目以降もおいしく飲むために、急須に湯が残らないよう最後の一滴まで注ぎましょう。 |
大福茶には深い歴史と、独特な楽しみ方があるようです。
日本茶の種類によって香りや味が違うので、いろいろな種類の大福茶を楽しんでみたいですね。
みなさんも、お正月に大福茶を飲んで一年の無病息災を祈りながら、ゆっくりしてはいかがでしょうか。
 ★参考HP
★参考HP「ochao」
★おいしいお茶の入れ方参考HP
「おいしい日本茶、入りました」