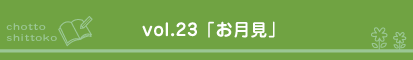
そろそろお月見の季節です。医院内でも月見団子やススキを飾ったりして、お月見を楽しんでみませんか?今回は、古くから親しまれているお月見についてご紹介します。
お月見は簡単に言うと、十五夜(旧暦8月15日)と、十三夜(旧暦9月13日)に満月を鑑賞する行事のことです。
お月見は中国から伝わったもので、平安時代に月を見ながら和歌を読み合う宴が催されるようになりました。
その後、江戸時代に収穫祭として庶民にも広まり、現在の私たちにも親しまれているのです。
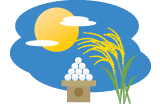
旧暦の8月、9月は1年の中で最も空が澄み、美しい満月が見れるとされており、今でもこの時期にお月見が行われています。
ちなみに、十五夜は旧暦の秋のちょうど真ん中の日に行われていたことから、「中秋の名月」とも呼ばれます。

旧暦を新暦に置き換え、十五夜が9月15日、十三夜が10月13日だと思っている方も多いでしょう。
しかし、月の満ち欠けを基準にした旧暦と、太陽の動きを基準にした現在の暦にズレが生じるため、新暦に置き換えると、十五夜と十三夜は毎年違う日になるのです。
ちなみに、今年2008年の十五夜は9月14日、十三夜は10月11日になります。

お月見は江戸時代から収穫を祈る祭りであったため、稲穂に似ているススキを飾るようになったと言われています。
また、ススキは鋭い切り口が魔除けになるとされ、お月見の後に軒先に吊るしておく習慣もあるそうです。

「月の中でうさぎが餅をついている」というのは、仏教説話から来ていると言われおり、現在でもこの考えが定着しています。
しかし、月うさぎは万国共通ではありません。欧米では「女性の横顔」、ベトナムでは「木下で休む男の人」、南ヨーロッパでは「大きなハサミのカニ」など様々。
月は地球に対して常に同じ面を向けているので、世界中どこで見ても同じ模様のはずですが、国によって捉え方が違っておもしろいですね。

★参考HP
「お月見特集」
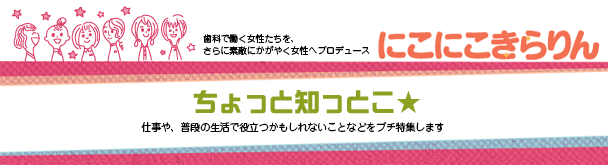
 ペーパークラフトで、お月見の飾りを作ってみませんか?受付や待合室に置いて、秋らしく飾り付けてみましょう。
ペーパークラフトで、お月見の飾りを作ってみませんか?受付や待合室に置いて、秋らしく飾り付けてみましょう。