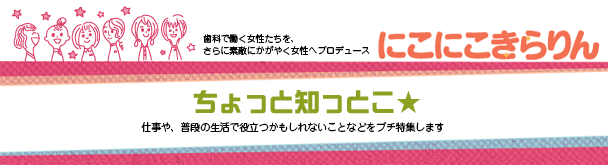今年もお正月が近づいてきました。お正月に食べるものといえば、「おせち料理」ですよね。毎年何気なく食べているおせち料理ですが、その歴史は古く、深い意味も込められています。今回は、おせち料理についてご紹介します。
「おせち」という言葉は、「御節供(おせつく)」が変化したものです。もともとは平安時代の宮廷行事で、季節の変わり目である五節句の日に、神にお供えしていた料理のことを「おせち」と呼んでいました。しだいに、1年で一番大切なお正月料理だけに「おせち」という言葉が、今日まで残ったと言われています。

おせち料理には、ひとつひとつ意味が込められています。その多くは、無病息災や子孫繁栄を願ったものです。ここでいくつか見てみましょう。
 無病息災 |
 子孫繁栄 |
 豊年豊作祈願 |
||
 長寿 |
 放念と息災 |
 子宝 |
||
★おせち料理の代表として、関東地方では黒豆、数の子、たつくりの三種、関西地方では黒豆、数の子、たたきごぼうの三種を、「祝い肴」や「三つ肴」と呼んでいます。
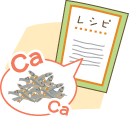 おせち料理である「たつくり」は、カルシウムが豊富で歯にとても良い食べ物。作り方も簡単なのでおすすめです。ミニレシピを印刷し、受付などに置いて来院された患者さんにプレゼントしましょう♪
おせち料理である「たつくり」は、カルシウムが豊富で歯にとても良い食べ物。作り方も簡単なのでおすすめです。ミニレシピを印刷し、受付などに置いて来院された患者さんにプレゼントしましょう♪→ミニレシピのダウンロードはコチラ
(大きさはハガキサイズです)
★参考HP
All About
「日本の伝統食 おせち料理豆知識」より