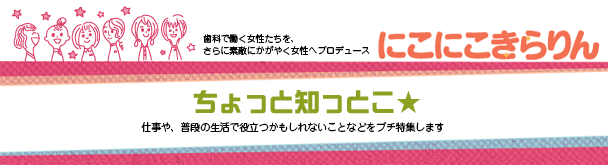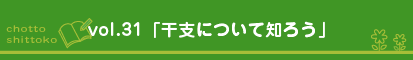
みなさん、あけましておめでとうございます。さて、今年2009年の干支は「丑」ですね。今回は、昔から親しんでいる干支の歴史と豆知識をご紹介します。
その歴史は中国からです。もともと「子、丑、寅、…」は、東西南北を十二に分け、あてはめられた漢字でした。これを民衆にも覚えやすくするために、さらに動物がそこへ当てはめられたのです。後に、日本では江戸時代から浸透し、一年ごとにめぐる動物として親しまれるようになりました。
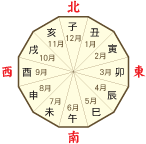
この理由として有名な民話があり、「足の遅い牛は、十二支に選ばれるために神様のもとへ向けて一番早く出かけました。しかし到着すると、こっそり牛の背中に隠れていたネズミがぴょんと飛び降り、一番になってしまいました。」というもの。これは、アジアの多くの国でも語り継がれています。
★詳しい話はこちらから
★詳しい話はこちらから
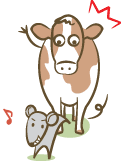
お正月の周りのものは、縁起の良い意味が込められているものが多くあります。十二支にも一つ一つその動物に合った意味が込められています。今年の干支「丑」は、「肉は大切な食料に、力は労働にと社会に密接に関わる動物」で、「粘り強さと誠実さ」を意味するそうです。

干支は、日本や中国に限ったものではありません。ロシアやモンゴル、ベルラーシなどのアジアの広い地域でも干支が存在します。日本の十二支とほぼ同じ動物ですが、チベット、タイ、ベトナム、ベルラーシでは「猫」、モンゴルでは「豹」など、ちょっと違った動物も見られます。
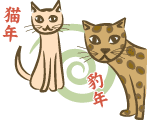
干支はお正月に欠かせない動物たちです。干支について知れば、その年の動物もちょっと違って見られそうですね。
★参考HP
「干支情報サイト」