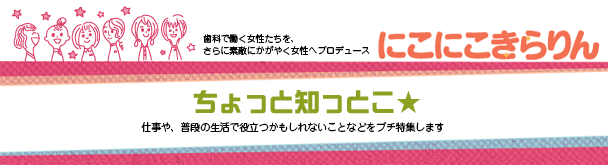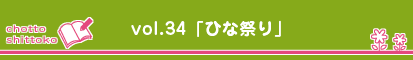
今回は、ひな祭りの歴史や豆知識をご紹介の他、 かんたんに作れるひな人形がダウンロードできますので、 院内の飾り付けに作ってみてはいかがでしょうか★

300年頃の古代中国で起こった、3月の初めの巳の日に、紙で作った人形を体に触れてけがれや災いを人形に移し川に流すという、
上巳節 (3月上旬の巳の日という意味)の風習が 遣唐使により、日本に伝えられたのが始まりです。この風習は平安時代の宮中行事となり、 そのころ宮中や
貴族たちの間で流行した人形遊びの「ひいな遊び」と結びつき、「流し雛(びな)」となりました。江戸時代には川に流さずに飾り、女の子の健やかな成長と幸せを願う現在の「ひな祭り」となりました。
ひし型の由来は定かではありませんが、江戸初期は、ひしの実を入れた白い餅を使っていました。 この実は、子孫繁栄と長寿の力があるとされているため、これを模してひし型になったという説があります。 3色の意味にも諸説がありますが、まとめると次のようになります。
 |
桃の花をイメージ。赤いクチナシの実には、解毒作用がある。赤は魔よけの色。 |
 |
純白の雪をイメージ。血圧を下げるひしの実が入り、子孫繁栄、長寿、純潔を願う。 |
 |
新緑をイメージ。強い香りで厄除け効果があるよもぎ餅。健やかな成長を願う。 |
五節句は江戸幕府によって定められたものなので、主流が関東風になっても不思議ではありませんが、 ひな遊びは平安時代の宮中や貴族たちから始まったものですし、京菓子司(宮中御用達のお菓子職人)が 発案したという話もあり、京都が発祥、つまり関西風が元祖だと考えられています。 ひなあられの色はひし餅と同じですが、黄色を入れて四季をあらす場合もあります。
 |
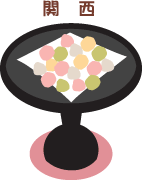 | |
|
米粒大で甘い。 江戸で米をじかに炒って作る爆米(はぜ)という菓子が流行っており、それを『ひなあられ』と命名したから…など諸説あります。 |
直径1センチ程度の大きさがあり、しょう油や塩味などがあります。
元々ひな祭りにかかせないひし餅を砕いて炒ったのが始まりとされています。 |
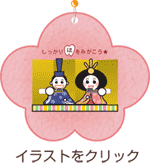 今回は歯をみがいているひな人形のクラフトです。
院内に飾ったり、患者さんへのおまけとしても活用できます★
今回は歯をみがいているひな人形のクラフトです。
院内に飾ったり、患者さんへのおまけとしても活用できます★ダウンロードは右のイラストをクリック してください→
(A4の厚紙で印刷することをおすすめします)
★参考HP
All About
ひなまつり♪桃の節句(3月3日)より