
2月3日は節分です。節分は古くから伝わり、春を迎える1年の節目ともいえる行事です。ここで一度、節分の歴史と豆まきのしかたを知っておきましょう。
日本では昔から、穀物や果実には「邪気を払う霊力」があるとされています。その「邪気」というのは形の見えない災害や病、飢饉などを指し、「鬼」の仕業だと考えられていました。また、邪気は季節の変わり目に入りやすいものです。そのため、節分の日に鬼に豆をぶつけて邪気(おに)を払い、福を呼びこむようになったのです。

豆まきのしかたは、地方によって多少異なりますが、ここでは一般的な方法をご紹介します。
福豆とは、炒った大豆のことです。豆を炒り、豆まきをする夜までは枡などに入れ、神棚にお供えしておきます。 |
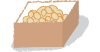 |
必ず全員で、夜に行いましょう。豆をまくのは一家の主人や長男の役目とされていますが、全員でまいても良いでしょう。 |
 |
まずは、外に向けて「鬼は外!」と2回豆をまきます。次に、鬼が入ってこないように戸を閉めてから内に「福は内!」と2回まきます。奥の部屋から順番に、玄関までまきましょう。 |
 |
豆まきが終わったら、1年の厄除けを願い豆を食べます。数え年(自分の年齢に1つ足したもの)の分だけ食べましょう。 |
 |
★参考HP
All About
節分3:押さえておきたい「豆まき」のツボより
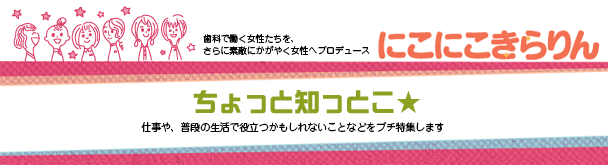
 いつもは豆まきをしない医院さんも、今年は医院の福を願って、豆まきをしてみませんか?
いつもは豆まきをしない医院さんも、今年は医院の福を願って、豆まきをしてみませんか?